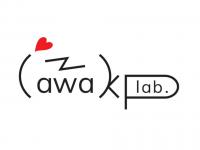神戸大学大学院保健学研究科の石原広大博士研究員(現:甲南女子大学看護リハビリテーション学部 助教)と井澤和大准教授、科学技術イノベーション研究科の山下智也教授、医学研究科の平田健一名誉教授らの研究グループは、日本全国の大規模データを分析し、急性心筋梗塞※1患者において低体重(BMI 〈体格指数〉※2が18.5kg/m2未満)と認知症が重なると院内死亡率を増加させることを明らかにしました。院内死亡率は、「低体重かつ認知症あり」群が最も高く17.5%、次いで「非低体重かつ認知症あり」群が13.2%、「低体重かつ認知症なし」群が11.6%、最も低かったのは、「非低体重かつ認知症なし」群の5.0%でした。また、75歳未満においては、両者の組み合わせによる影響が特に顕著であることも示されました。高リスク患者をいち早く発見し、迅速かつ適切なケアを提供することで、急性心筋梗塞患者における死亡率のさらなる低下や入院期間の短縮が期待されます。このアプローチにより患者の予後が向上するだけでなく、効率的で持続可能な医療体制の発展へとつながる可能性があります。
この成果は2025年8月4日付で「European Journal of Cardiovascular Nursing」に掲載されました。

ポイント
- 本研究は、低体重と認知症が同時にあることで急性心筋梗塞患者の院内死亡リスクが高まることを、日本全国の大規模データを用いて初めて明らかにしました。
- 特に75歳未満の急性心筋梗塞患者で影響が大きく、早期診断と個別対応が重要であることが示され、今後の医療判断に役立つ知見となりました。
- 低体重と認知症を併存する高リスク患者を早期に見つけて適切にケアすることで、急性心筋梗塞患者の院内死亡率の低下と入院期間の短縮につながり、患者の予後改善や医療の効率化が期待されます。
研究の背景
低体重や認知症がそれぞれ死亡率に及ぼす影響についてはこれまでにも明らかにされてきました。しかし、それらが同時に存在した場合に急性心筋梗塞患者の院内死亡率に与える影響については、十分に検証された大規模研究は存在していませんでした。高齢化が進む日本において、栄養状態や認知機能の低下が心血管疾患の予後に与える影響を包括的に評価することは、臨床現場におけるリスク管理の観点からも極めて重要です。我々は、全国的な大規模データベースを用いて、急性心筋梗塞患者における低体重と認知症の併存が院内死亡率に与える影響を調査しました。
研究の内容
本研究では、日本循環器学会が主導しているJROAD-DPC ※3 (Japanese Registry of All Cardiac and Vascular Diseases Diagnosis Procedure Combination)を用いて、2012年4月から2021年3月までに登録された474,979名の急性心筋梗塞患者を対象に、低体重(BMI <18.5kg/m?)と認知症の有無による院内死亡率への影響を検討しました。患者はBMIと認知症の有無により「低体重かつ認知症あり」「非低体重かつ認知症あり」「低体重かつ認知症なし」「非低体重かつ認知症なし」の4群に分類され、多階層混合効果ロジスティック回帰分析を用いて評価を行いました。
その結果、院内死亡率が最も高かったのは「低体重かつ認知症あり」の群で17.5%に達し、「非低体重かつ認知症あり」群が13.2%、「低体重かつ認知症なし」群が11.6%、「非低体重かつ認知症なし」群が5.0%と、両因子の併存が院内死亡率を著しく上昇させることが示されました。さらに年齢別のサブグループ解析では、75歳未満の急性心筋梗塞患者において低体重と認知症の併存が特に顕著であることが明らかとなりました。
今後の展開
本研究により、低体重と認知症の併存が急性心筋梗塞患者の院内死亡率リスクを増加させることが示されました。特に75歳未満における影響が大きいことから、早期発見と適切な管理の重要性が改めて浮き彫りになりました。急性心筋梗塞患者や心不全患者に対しては、早期からの認知機能評価を実施し、運動療法と認知機能トレーニングを組み合わせた介入による認知機能の維持?改善可能性について今後検討していく予定です。
さらに、75歳未満の適正体重の維持が重要であることが明らかになりました。特に低体重を予防することで認知機能低下のリスクを軽減できる可能性があります。この課題に対しては、予防的介入や栄養管理の観点から多角的な検討が求められます。
用語解説
※1 急性心筋梗塞
心臓の筋肉に酸素と栄養を供給している冠動脈の一部に急速な血栓性閉塞が生じ、心臓の筋肉の一部が壊死を来す疾患。
※2 BMI(Body Mass Index:体格指数)
体重(kg)を身長(m)の二乗で割ることで算出される、肥満度を評価するための指標。本研究では、WHOアジア基準に基づき、以下の2区分で分類した:低体重(BMI <18.5 kg/m?)、非低体重(BMI ≥18.5 kg/m?)。
※3 JROAD-DPC(Japanese Registry of All Cardiac and Vascular Diseases Diagnosis Procedure Combination)
日本循環器学会が主導する全国規模のデータベースで、参加病院から収集されたDPC(診断群分類)データをもとに、循環器疾患に関する病名や診療行為の詳細を網羅している。現在、1,000以上の医療施設が参加しており、得られた情報は循環器診療の質向上を目的とした基礎資料として活用されている。
謝辞
本研究は、JSPS 科研費 JP22K11392、JP22K19708 の支援を得て実施されました。
論文情報
タイトル
DOI
10.1093/eurjcn/zvaf158
著者
Kodai Ishihara1,2; Masato Ogawa1,3,4; Yuji Kanejima1,5; Naofumi Yoshida 6;Koshiro Kanaoka 7; Yoko Sumita 7;Yoshitaka Iwanaga 7;Yoshihiro Miyamoto 7;Tomoya Yamashita 8;Yoshitada Sakai 3; Ken-Ichi Hirata 9; Kazuhiro P Izawa 1
- Department of Public Health, Graduate School of Health Sciences, Kobe University, Hyogo, Japan.
- Department of Physical Therapy, Faculty of Nursing and Rehabilitation, Konan Women's University, Hyogo, Japan.
- Division of Rehabilitation Medicine, Kobe University Graduate School of Medicine, Hyogo, Japan.
- Department of Rehabilitation Science, Osaka Health Science University, Osaka, Japan.
- Department of Rehabilitation, Kobe City Medical Center General Hospital, Hyogo, Japan.
- Department of Cardiovascular Aging, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka, Japan.
- Department of Medical and Health Information Management, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka, Japan.
- Department of Advanced Medical Science, Kobe University Graduate School of Science, Technology and Innovation, Hyogo, Japan.
- Division of Cardiovascular Medicine, Department of Internal Medicine, Kobe University Graduate School of Medicine, Hyogo, Japan.
掲載誌
European Journal of Cardiovascular Nursing